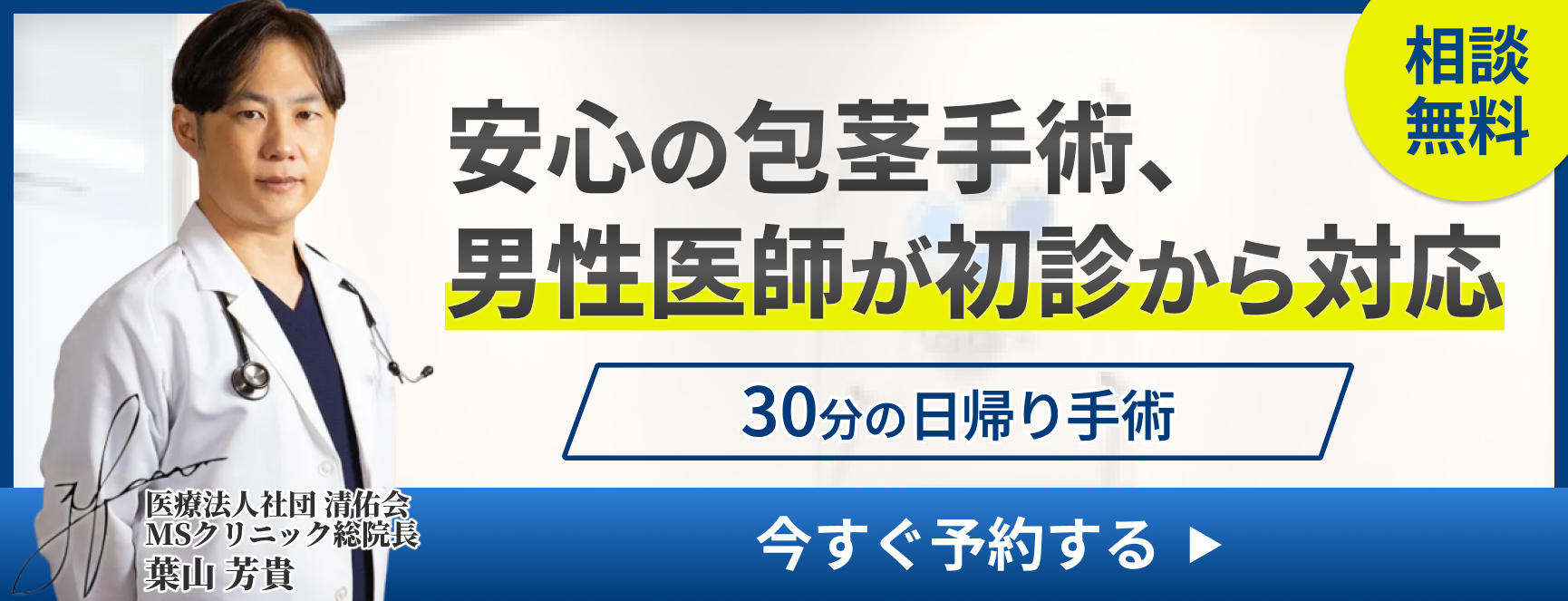精液量が多い人の特徴とは?体質や生活習慣との関係を解説
- 更新日:2025.06.25
- 投稿日:2025.06.24
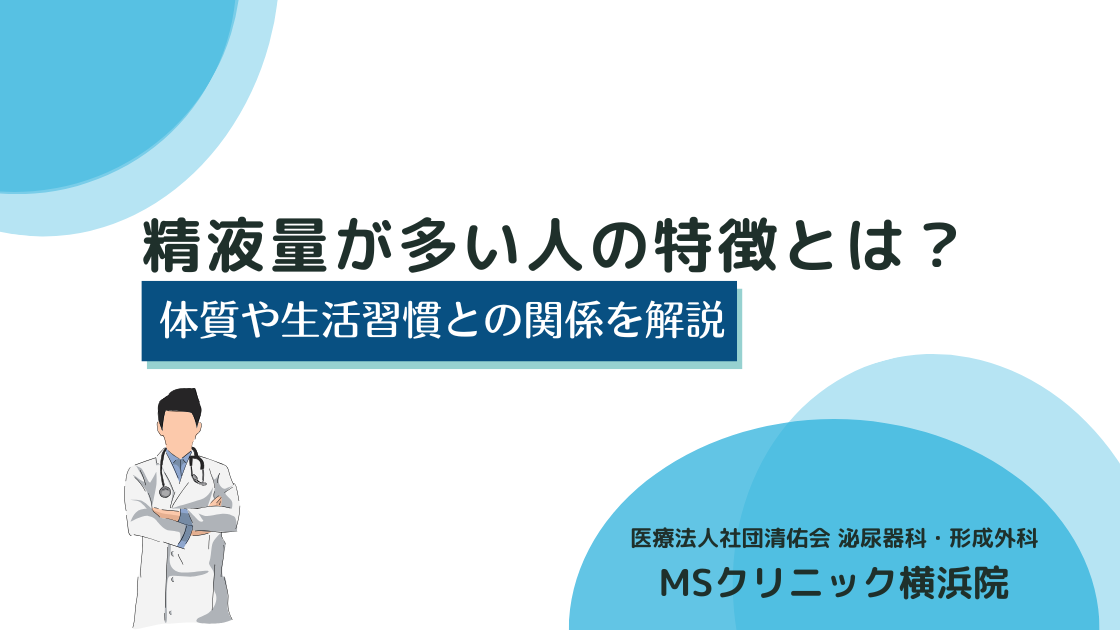
精液の量に悩んでいませんか?精液量は、健康状態を知る目安の一つで、男性ホルモンや生活習慣、年齢などのさまざまな要因で多くなる可能性があります。この記事では、精液量について、以下の内容を解説します。
- 精液量が多い人の特徴7選
- 精液量を増やすセルフケア
- 医療機関を受診する目安
記事を読めば、精液量が多い人の特徴や、適切な量を保つためのセルフケアを正しく理解できます。自身の状態と照らし合わせながら、健康管理のきっかけにしてください。
当院では、精液の量にお悩みの方の相談にも対応しております。無料の診察カウンセリングを行っておりますので、一人で抱え込まずにまずはご相談ください。
>>予約から治療の流れについて
精液量が多い人の特徴7選
精液量が多い人の特徴について、以下の7つを解説します。
- テストステロンの値が高い
- 水分摂取量が多い
- 正しい食生活を送っている
- 十分な睡眠を確保している
- 禁欲期間を設けている
- タバコやアルコールを避けている
- サウナや長風呂をしない
テストステロンの値が高い
テストステロンは、男性ホルモンの一種で、精巣で作られます。テストステロンは、筋肉や骨格の発達、体毛の増加、性欲の向上、精液の生成などに関係しています。思春期を迎えると、テストステロンの分泌が増加し、20〜30代前半でピークを迎え、30代後半から徐々に低下していきます。
テストステロンの値が高い人は、精液量が多い傾向があります。テストステロンは、精嚢(せいのう)に作用し、精液の主要成分である精漿(せいしょう)の産生を促進します。遺伝的な要因や生活習慣もテストステロン値に影響を与え、精液量には個人差があります。
BMIが25未満の標準体重の場合、肥満の場合に比べてテストステロン値が高く、精液量も多い傾向があります。一方、BMIが25以上の肥満になると、テストステロン値が低下しやすくなります。
以下の記事では、テストステロンの低下に関わる「性欲減退」の原因や改善策について、医師の視点から詳しく解説しています。加齢やストレス、生活習慣の影響など、気になる症状がある方は参考にしてください。
>>男性の性欲減退の原因と対策!経験豊富な医師が教える回復のための鍵
水分摂取量が多い
精液の約90%は水分でできており、血液から作られます。水分摂取量が多いと、体内の水分が保たれ、血流が良くなるため、精液量が多くなる可能性があります。こまめに水分を摂り、体内の水分バランスを保つことが精液量の維持に役立ちます。
正しい食生活を送っている
バランスの良い食事は、健康な体を維持するために重要です。精液の生成に必要な以下の栄養素をバランス良く摂取することで、精液量や精子の質の向上につながる可能性があります。
- 亜鉛:牡蠣やレバー、赤身肉、魚、卵、カシューナッツ
- アルギニン:大豆やマグロ、卵
- ビタミンE:ナッツ類や卵、緑黄色野菜
- ビタミンD:きのこ類や魚介類
- ビタミンK:納豆や海藻類、緑黄色野菜
- DHEA:山芋や里芋、アボカド
十分な睡眠を確保している
睡眠は、ホルモンバランスを調整したり、体を修復したりするうえで大切です。質の高い睡眠を十分に取ると、テストステロンの分泌が安定し、精液量が多くなる傾向があります。睡眠不足や過剰な睡眠は、ホルモンバランスを崩し、精液量に悪影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
禁欲期間を設けている
禁欲期間の長さは、精液量に影響を与えます。禁欲期間が長すぎると、精液が古くなり、精子の質が低下する可能性があります。WHO(世界保健機関)のマニュアルでは、精液検査のために2〜7日間の禁欲を推奨しています。
タバコやアルコールを避けている
喫煙や過度の飲酒は、精子の質や量に悪影響を及ぼす可能性があります。タバコに含まれる物質は、精子のDNAを損傷し、アルコールは、テストステロンの分泌を抑制する可能性があります。
サウナや長風呂をしない
精巣は、体温よりも低い温度で正常に機能します。サウナや長風呂は、精巣の温度を上昇させ、精子の生成に悪影響を及ぼす可能性があります。精液量が気になる場合は、サウナや長風呂を控えめにしましょう。
精液量を増やすセルフケア
精液量を増やすためのセルフケアについて、以下の5つの方法を解説します。
- 適切な水分摂取
- 精液に必要な栄養を含む食事
- 睡眠の質の改善
- 適度な運動
- 禁欲期間のコントロール
5つのセルフケアは、精液量の改善だけでなく、全身の健康維持にも効果が期待できます。継続的に取り組むことをおすすめします。
適切な水分摂取
厚生労働省の報告によると、1日の水分摂取量の目安は、食事を含めて2.3〜3.5リットルです。過剰な摂取は体に負担をかける可能性があるため、適量を心がけることが大切です。カフェインを多く含むコーヒーや緑茶などは、利尿作用があるため、水分補給には適していません。ノンカフェインの飲み物や水をこまめに摂取しましょう。
精液に必要な栄養を含む食事
精液の生成に必要な亜鉛やアルギニン、ビタミンEなどの栄養素を積極的に摂取しましょう。亜鉛は、細胞の成長や分裂に必要なミネラルです。アルギニンは、アミノ酸の一種で、血管拡張作用があり、精巣への血流を促進する効果が期待できます。ビタミンEは、抗酸化作用があり、精子を酸化ストレスから保護するサポートをします。
バランスの良い食事を心がけ、必要な栄養素を積極的に摂取することで、精液量の増加が期待できます。サプリメントなどで過剰に摂取すると、健康に悪影響を及ぼす可能性もあるため、食品からバランス良く摂取することが重要です。
睡眠の質の改善
精子の生成や精液量に影響を与える男性ホルモンは、睡眠中に分泌が促進されるため、質の高い睡眠を十分に取ることが重要です。海外の研究では、7〜7.5時間の睡眠が、精液量にとって最適であるとされています。適切な睡眠時間を維持するように意識しましょう。
適度な運動
適度な運動は、血行を促進し、精巣への血流を良くする効果が期待できます。精巣への血流が良くなると、精子の生成が促進され、精液量が増加する可能性があります。以下の運動を週に3~5回、30分程度、継続的に行いましょう。
- 有酸素運動(ウォーキングやジョギングなど)
- 下半身の筋力トレーニング(スクワットなど)
有酸素運動は、心肺機能を高め、血行を改善する効果があります。下半身の筋力トレーニングは、精巣周辺の筋肉を鍛え、血流を促進する効果が期待できます。過度な運動は体に負担をかけ、逆効果になる可能性があるため、自身の体力に合わせて無理のない範囲で行うことが大切です。
禁欲期間のコントロール
8日以上の長期の禁欲は、精子の運動率低下やDNA損傷などのリスクを高める可能性があります。精液量を増やすためには、3日以上の禁欲が続かないように心がけることが大切です。精液量に不安がある場合は、医療機関への相談も検討しましょう。
医療機関を受診する目安
精液の状態は、個人差が大きいため、量や色の明確な基準はありません。自身の精液の状態を普段から把握しておき、変化に気づくことが大切です。以下の変化がある場合は、放置せずに医療機関への相談を検討してください。
- 精液の量が急増・急減した
- 精液に悪臭を伴う
- いつもと精液の色が違う
精液の量が急増・急減した
WHO(世界保健機関)のマニュアルで、精液量の正常値は1.4mL以上とされています。体質や生活習慣、年齢などによって精液量は変動し、医学的には精液量の上限は設けられていません。一時的な精液量の増減であれば問題ない場合が多いですが、急激に増減した場合や、増減が3か月以上続く場合は、注意が必要です。
精液量の急激な変化は、前立腺炎や精嚢炎といった炎症のサインの可能性があります。炎症で精液を作る組織が刺激され、過剰に精液が産生されることがあります。加齢でテストステロンが減少し、精液量が少なくなることもあります。気になる点があれば、放置せずに早めに医療機関へ相談してください。
精液に悪臭を伴う
健康な状態の精液は、少し甘酸っぱい臭いがします。性感染症などに感染した場合、感染した細菌が精液中で増殖し、生臭いことがあります。前立腺炎や精嚢炎などの炎症でも、精液に悪臭を伴う場合があります。悪臭に気づいたら、自己判断せずに、すぐに泌尿器科を受診しましょう。
当院では精液に関するお悩みにも対応しています。診察カウンセリングを無料で行っておりますので、ご予約のうえご来院ください。
>>MSクリニックで予約する
いつもと精液の色が違う
健康な状態の精液は、白っぽいクリーム色をしています。精液が以下の色の場合は、注意が必要です。
- 茶褐色や赤みを帯びている
- 黄緑色っぽい
茶褐色や赤みを帯びている場合は、前立腺肥大症や前立腺がん、精嚢炎による炎症などが原因で出血し、精液に血が混じっている可能性があります。黄緑色っぽい場合は、性感染症や前立腺炎などが原因で炎症が起こり、精液に膿が混じり、黄緑色っぽくなることがあります。
精液の色に変化が見られた場合は、早めに泌尿器科を受診しましょう。放置すると症状が悪化したり、病気の発見が遅れたりする可能性があります。
まとめ
精液量は、健康状態を知る目安の一つで、テストステロン値や水分摂取量、食生活、睡眠、禁欲期間、喫煙や飲酒、サウナや長風呂などの習慣が影響します。精液量を増やすためには、水分補給や栄養・睡眠管理、適度な運動などのセルフケアが有効な可能性があります。
精液量には個人差があるため、急激な増減や悪臭、色の変化などがある場合は、前立腺や精嚢の病気が原因の可能性があります。自身の状態を把握し、気になることがあれば、早めに泌尿器科を受診しましょう。
以下の記事では、40代男性に多く見られる性欲の減退について、加齢に伴う身体的・心理的な変化や、その改善に向けた具体的なアプローチを詳しく解説しています。心当たりがある方はぜひご覧ください。
>>40代男性の性欲減退の原因とは?心身の変化と改善アプローチ
参考文献
- 厚生労働省:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書(令和7年)
- Qing Chen, Huan Yang, Niya Zhou, Lei Sun, Huaqiong Bao, Lu Tan, Hongqiang Chen, Xi Ling, Guowei Zhang, Linping Huang, Lianbing Li, Mingfu Ma, Hao Yang, Xiaogang Wang, Peng Zou, Kaige Peng, Taixiu Liu, Zhihong Cui, Lin Ao, Till Roenneberg, Ziyuan Zhou, Jia Cao.Inverse U-shaped Association between Sleep Duration and Semen Quality: Longitudinal Observational Study (MARHCS) in Chongqing, China.Sleep,2016,39,1,p.79-86
- WHO(世界保健機関):WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen, 6th ed(2021年)
ページ監修:総院長「葉山芳貴」紹介

総院長、医学博士 葉山芳貴
経歴
- 平成14年
- 聖マリアンナ医科大学 卒業
- 平成20年
- 大阪医科大学 大学院 卒業
- 平成22年
- 大手美容形成外科 院長 就任
- 平成27年
- メンズサポートクリニック開設
- 平成28年
- メンズサポートクリニック新宿 院長就任
- 平成28年
- 医療法人清佑会 理事長 就任
資格
医師免許(医籍登録番号:453182)
保険医登録(保険医登録番号:阪医52752)