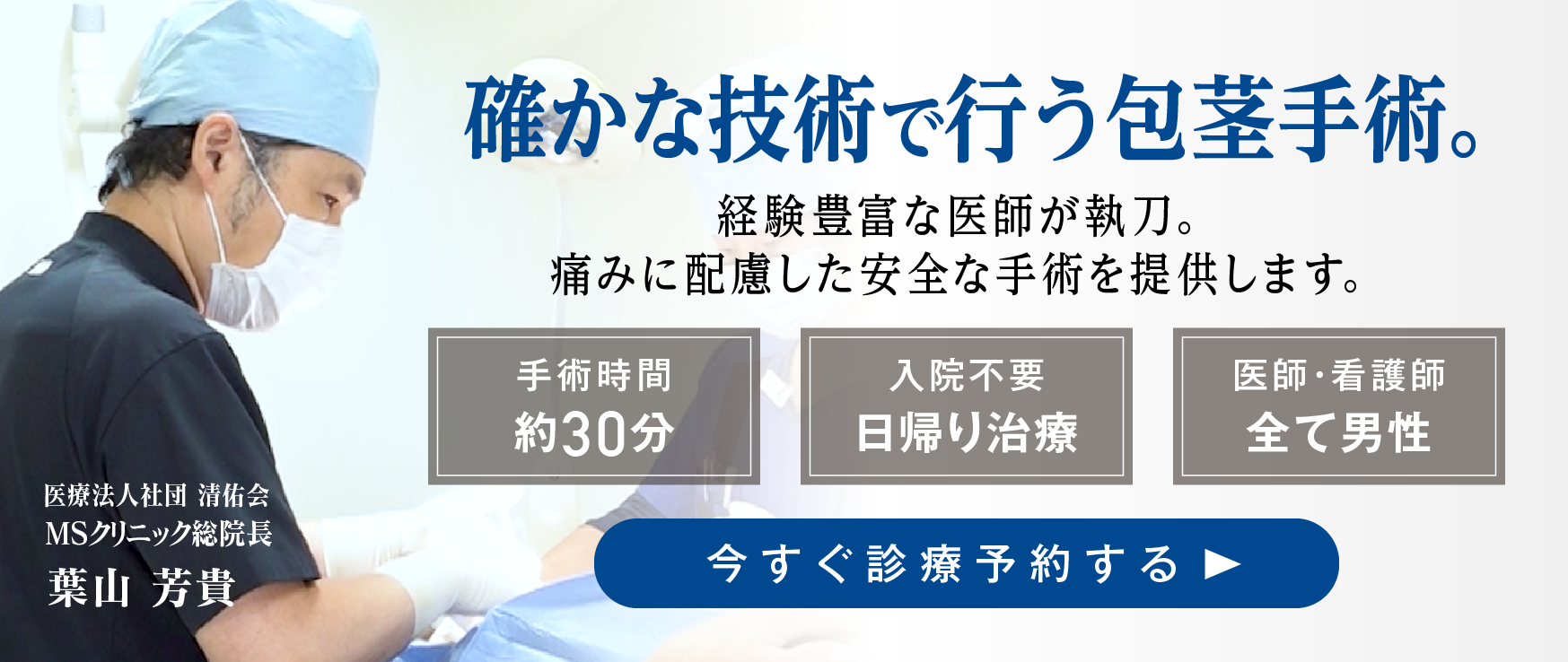包茎は遺伝なの?先天性・後天性の違いや環境要因との関連性を解説
- 更新日:2025.06.04
- 投稿日:2025.05.25
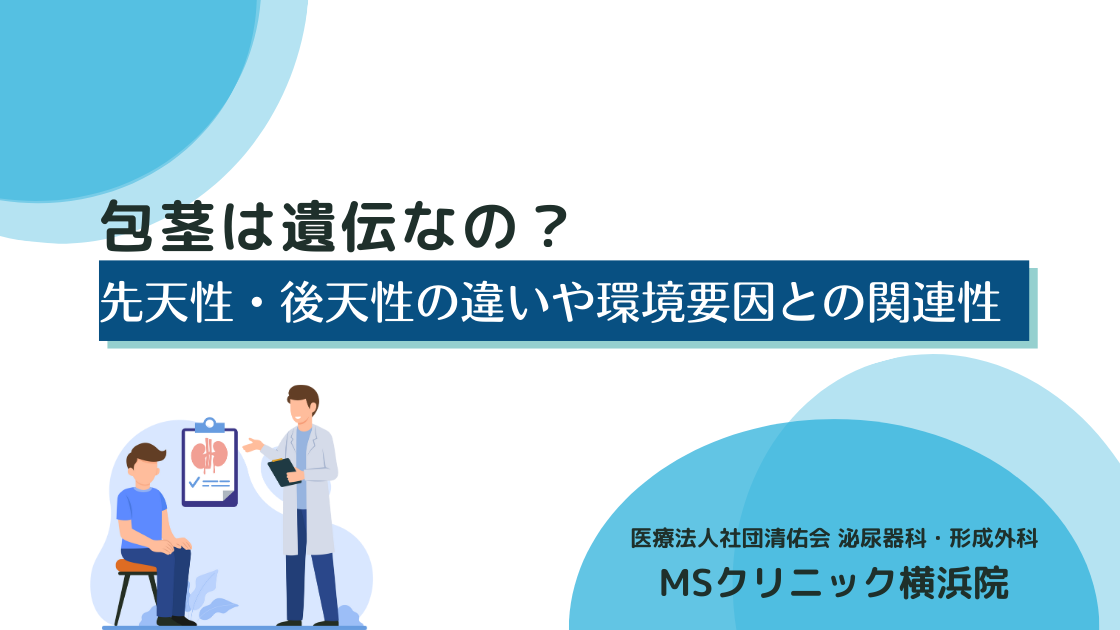
包茎に関するさまざまな疑問や不安を抱えている方は多くいます。生まれたばかりの赤ちゃんは包茎の状態ですが、成長とともに改善されることが多いです。この記事では、治療が必要なケースや先天性と後天性の違い、原因、特徴などを解説します。包茎によって引き起こされる症状やリスク、具体的な治療法も紹介します。
包茎はデリケートな問題だからこそ、正しい知識を身につけることが大切です。記事を通して包茎に関する理解を深め、ご自身やパートナー、お子さんが抱える悩みを解消し、前向きな一歩を踏み出しましょう。
当院では仮性包茎や真性包茎、カントン包茎についてのお悩み相談も受け付けています。不安を感じている方は当院公式サイトをご確認ください。
先天性包茎と後天性包茎の違い
包茎とは包皮が亀頭を覆い容易に剥けない状態を指し、以下の種類があります。
- 仮性包茎:包皮が亀頭を覆っているが、手で簡単に剥ける
- 真性包茎:包皮の先端が狭くなっており、亀頭を露出できない
- カントン包茎:手で剥くことはできるが、包皮が亀頭直下に嵌まり込んでしまう
思春期頃までには自然に改善されることが多いですが、症状が続く場合は治療が必要なケースもあります。ご自身の状況を理解し適切な対応をするために、以下の2点に沿って解説します。
- 先天性包茎とは?自然に治る可能性がある状態
- 後天性包茎とは?炎症や外傷など後天的に狭くなる状態
先天性包茎とは?自然に治る可能性がある状態
先天性包茎とは「生理的包茎」とも言われ、生まれたときから包皮が亀頭を覆っていて剥けない状態のことです。胎児期に包皮と亀頭が癒着しているためで、異常なことではありません。
先天性包茎の場合、3歳頃までに包皮が剥ける子もいれば、思春期頃までかかる子もいます。清潔を保ち、自然に皮が剥けるのを待ちましょう。
後天性包茎とは?炎症や外傷など後天的に狭くなる状態
後天性包茎とは、成長過程で何らかの原因によって包皮の先端が狭くなり、亀頭を覆ったままの状態になることを指します。後天性包茎は、幼少期や思春期以降に発症します。炎症や外傷、感染症、肥満などが原因です。
後天性包茎の場合、自然に治ることは少なく、衛生状態が悪化すると症状も悪化する可能性があります。亀頭包皮炎を繰り返す、排尿が困難である、痛みがあるなどの症状を伴う場合は、医療機関を受診しましょう。
ご自身の包茎の種類がわからないという方は、ご来院前にできる包茎チェックをしましょう。以下から30秒でセルフチェックができるので、気になる方は確認してみてください。
>>包茎のセルフチェックを受ける
包茎の原因は遺伝?それとも環境?
包茎の原因が、遺伝的要因か環境的要因か不安に思う方がいます。2つの要因について、以下に解説します。
- 遺伝的要因と家族傾向の可能性
- 環境要因:衛生状態・肥満・炎症の影響
遺伝的要因と家族傾向の可能性
包茎自体は遺伝するものではありません。一方で、ペニスのサイズは遺伝する可能性があり、ペニスが小さいと包皮が亀頭を覆い、包茎の状態になりやすいと考えられています。
包皮の柔軟性も遺伝する可能性があり、包皮が硬いと成長しても包皮が剥けにくく、包茎の状態が続く可能性があります。亀頭と包皮がくっついている癒着の期間の長さも遺伝的影響を受ける場合があり、癒着している期間が長いほど包茎の状態が長引く可能性が高いです。
包茎になりやすい体質が遺伝する可能性はあるものの、包茎そのものは遺伝しないことを理解しましょう。
環境要因:衛生状態・肥満・炎症の影響
包茎には遺伝的要因だけでなく、環境要因も関わっている可能性があります。後天性包茎は環境要因が原因となる場合が多く、主に以下のケースがあります。
|
原因 |
説明 |
注意点 |
|
衛生状態の悪化 |
恥垢や汚れが溜まり、炎症を起こしやすくなる |
亀頭包皮炎を繰り返すと包皮が慢性的に炎症を起こし、線維化して硬くなってしまう |
|
肥満 |
ペニスの根元周辺に脂肪が蓄積し、包皮が押し出されて包茎の状態になりやすい |
ペニスが脂肪に埋もれ、包皮が押し出され後天性包茎になることがある |
|
炎症 |
炎症を繰り返すと治癒過程で包皮が硬くなり、包茎の状態になりやすい |
包茎の状態が慢性化され、自然に治る可能性が低くなる |
|
外傷 |
包皮に傷がつくと傷の治癒過程で包皮が硬くなり、包茎になることがある |
無理に包皮を剥こうとしたり、性行為で強い摩擦が生じたりすることで、包皮に傷がつくことがある |
環境要因は生活習慣の改善によって予防・改善できる可能性があります。日頃から清潔にし、バランスの良い食事や適度な運動を心がけることは、包茎の予防だけでなく健康全般にとっても重要です。
包茎によって起こりうる症状とリスク
包茎は病気ではありませんが、適切なケアが必要です。包茎によって引き起こされる主な症状とリスクは以下のとおりです。
- 痛み・かゆみ・炎症
- 衛生状態の悪化と亀頭包皮炎
- 性行為や排尿への支障
- 進行によるリスク(陰茎がんなど)
痛み・かゆみ・炎症
包茎の状態によって、包皮の内側に汚れや恥垢が溜まりやすくなります。恥垢は皮膚の古い角質や皮脂腺から分泌される脂などが混ざったもので、痛みやかゆみ、炎症を引き起こすことがあります。包皮の先端が狭くなっている真性包茎の場合、亀頭を清潔に保つことが難しく炎症が起こりやすい状態です。
炎症は、体が異物や刺激から身を守ろうとする自然な反応です。炎症が起こると、施術部位に以下の症状が現れることがあります。
- 赤く腫れ上がる
- 熱を持つ
- 痛みやかゆみを感じる
体が治癒しようとするサインですが放置すると慢性化し、深刻な問題につながる可能性があります。
衛生状態の悪化と亀頭包皮炎
包茎は衛生状態の悪化につながる可能性があります。亀頭を清潔に保てないため細菌が繁殖しやすく、亀頭包皮炎という炎症を起こすことがあります。亀頭包皮炎になると、以下の症状が現れることがあります。
- 痛み
- かゆみ
- 赤み
- 腫れ
- 膿
- 発熱
- 排尿痛
北京市で行われた研究では、亀頭包皮炎の男性のHPV(ヒトパピローマウイルス)検出率が40.77%と報告されています。HPVは性感染症の一つで、一部の型は子宮頸がんや陰茎がん、肛門がん、中咽頭がんなど、さまざまながんのリスクを高める可能性があります。
適切な衛生管理を行うことで、亀頭包皮炎などのリスクを軽減できる可能性があります。石鹸をよく泡立てて優しく洗い、しっかりとすすぐことが大切です。包皮を無理に剥こうとすると、傷つけて炎症を悪化させる可能性があります。包皮が剥けない場合は、無理に剥かずに医師に相談しましょう。
性行為や排尿への支障
包茎によって包皮が邪魔になり性行為がしづらかったり、痛みを伴ったりする場合があります。包皮の先端が狭いと尿の出口が塞がれ、排尿がスムーズにいかないこともあります。
性行為の際に痛みや不快感がある場合は、無理をせずパートナーとよく話し合うことが大切です。排尿が困難な場合は、尿路感染症のリスクが高まる可能性があるため、医療機関への受診をおすすめします。
進行によるリスク(陰茎がんなど)
包茎を放置すると、将来的に深刻な病気を引き起こすリスクがあります。一部の研究では、適切な衛生管理がなされない場合、陰茎がんのリスクに影響する可能性が報告されています。
陰茎がんは、ペニスの皮膚や亀頭にできるがんです。発生率は低いものの、包茎は危険因子の一つと考えられています。包茎によってHPVに感染すると陰茎がんのリスクが高まり、パートナーへのHPV感染リスクも高める可能性があります。
包茎は放置せずに医療機関に相談することで、症状の改善や合併症の予防が期待できます。気になる症状がある場合は、経験豊富な医師に相談することをおすすめします。
包茎の治療法
包茎の状態が続く場合は、治療が必要となるケースがあります。治療法は保存的療法と手術療法の2種類があり、それぞれメリット・デメリットがあります。ご自身の状況や希望に合わせて、医師と相談しながら最適な治療法を選択することが重要です。主な治療法について、以下の3点を解説します。
- 保存的療法(薬物治療・ステロイド軟膏)
- 手術の種類と選択肢(環状切除・部分切除)
- 医療機関での相談のタイミング
保存的療法(薬物治療・ステロイド軟膏)
保存的療法は、手術をせずに包茎を治療する方法です。主にステロイド軟膏を用いて包皮の炎症を抑えたり柔軟性を高めたりすることで、包皮を剥きやすくする効果が期待できます。
ステロイド外用薬は、抗炎症作用と免疫抑制作用を持つ薬です。包皮の炎症を抑え皮膚を薄くすることで包皮の柔軟性を高め、剥けやすくなる効果が期待できます。1日に数回、包皮の内側に少量の軟膏を塗布します。塗布量や頻度は、医師の指示に従いましょう。治療期間は数週間~数か月かかる場合があります。
ステロイド外用薬を使用する際の注意点として、自己判断で薬の使用を中止せず、医師の指示に従って治療を続けましょう。以下の副作用が現れる可能性があります。
- 皮膚の赤み
- 皮膚のかゆみ
- 色素沈着
効果が見られない場合や症状が悪化した場合、副作用が気になる場合は医師に相談しましょう。
手術の種類と選択肢(環状切除・部分切除)
保存的療法で効果が見られない場合や真性包茎の場合は、手術が必要になることがあります。包茎手術は日帰りで行えることが多く、一般的には入院の必要がない場合が多いです。手術の主な方法は、以下のとおりです。
- 包皮環状切除術:包皮を環状に切除する。手術時間は短く術後の回復も早い。
- 包皮部分切除術:包皮の一部を切除する。亀頭を覆う部分を残すため、自然な見た目になりやすい。
どちらの手術方法が適しているかは、包茎の状態や患者さんの希望によって異なります。医師とよく相談し、ご自身に合った方法を選択することが重要です。手術は一般的に局所麻酔で行われるため、日帰り手術となります。
医療機関での相談のタイミング
包茎は自然に治ることもありますが、以下の症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。
- 包皮が剥がれず、痛みを感じる
- 亀頭包皮炎を繰り返す
- 排尿時に違和感がある
- 性行為に支障がある
亀頭包皮炎を放置すると、炎症が重症化したり、性感染症などを併発したりするリスクがあります。異常を感じたら一人で悩まず、泌尿器科を受診し適切な診断と治療を受けましょう。
遺伝が心配な方へのアドバイス
生まれたばかりの赤ちゃんはほぼ全員が包茎の状態です。胎児期に包皮と亀頭が癒着しているためで、自然な生理現象です。成長とともに癒着は剥がれ、包皮が剥けるようになります。
ペニスのサイズや包皮の柔軟性などが遺伝し、包茎の状態に影響を与える可能性があります。ペニスが比較的小さいと包皮が亀頭を覆いやすく、包茎の状態になりやすいからです。包皮の柔軟性も遺伝する可能性があり、包皮が硬い場合、成長しても包皮が剥けにくく、包茎の状態が続く場合があります。
幼少期から包皮を優しく洗う習慣を身につけることで、包皮と亀頭の癒着が剥がれやすくなり、包茎の状態が緩和される可能性があります。
成長過程で自然に治ることもある
思春期を迎える頃には、ほとんどの男性で包皮が剥けるようになります。男性ホルモンの分泌が活発になることでペニスが成長し、包皮も伸びるためです。自然に治る可能性は、包茎の状態によって以下のとおり異なります。
- 仮性包茎:自然に治る可能性が高く、手で包皮を剥がすことができる状態
- 真性包茎:自然に治ることはほとんどない。包皮の先端が狭く、亀頭を露出できない状態
子供の包茎について考えるべきこと
お子さんの包茎は、年齢や包茎の状態、お子さん自身が困っているかについて考えることが大切です。幼少期は自然に改善する可能性が高いので、無理に包皮を剥こうとせずに清潔に保つよう心がけてください。入浴時に石鹸をよく泡立て、包皮の外側を丁寧に洗いましょう。
包皮を無理に引っ張ったり剥いたりすることは、炎症や傷につながる可能性があるため避けましょう。以下の症状が見られる場合は、医療機関へ相談することをおすすめします。
- 排尿時に痛みを伴う
- 炎症を繰り返す
- 尿の勢いが弱い
成長しても包茎の状態が続く場合は、日常生活への影響や将来的なリスクも考慮し、早めに医師に相談しましょう。
一人で悩まず医師に相談を
包茎はデリケートな問題であり、一人で悩む方が多いです。包茎に関する正しい情報を得るためには、専門の医師に相談することが重要です。医師は包茎の状態を正確に診断し、年齢や症状に合わせた適切なアドバイスや治療法の提案が期待できます。お子さんの包茎についても、小児科医や泌尿器科医に相談してみましょう。
まとめ
包茎には先天性と後天性があり、原因や特徴が異なります。先天性包茎は生まれたときから包皮が亀頭を覆っている状態で、成長とともに自然に改善されることが多いです。後天性包茎は、成長過程で炎症や外傷などにより包皮が狭くなることで起こる可能性があります。
包茎の原因は、遺伝的要因としてペニスの大きさや包皮の柔軟性などが挙げられます。環境要因としては、衛生状態の悪化や肥満、炎症などが影響します。包茎を放置すると、痛みやかゆみ、炎症、亀頭包皮炎などの症状が現れる可能性があります。衛生状態の悪化や性行為・排尿への支障のリスクも高まります。
治療法には保存的療法と手術療法があり、ステロイド軟膏を用いた保存的療法や包皮環状切除術、包皮部分切除術などがあります。痛みや炎症などの症状がある場合は、一人で悩まずに医療機関に相談しましょう。
以下の記事では、包茎の手術や治療、タイプや症状などについて網羅的に解説しています。包茎にお悩みのある方はぜひチェックしてみてください。
>>包茎のお悩み、包茎手術は男性専門泌尿器形成のMSクリニック横浜へ
参考文献
- Wang S, Ma QY, Du J, Wei TT, Zhang WX, Wang P, Zhou Y, Wei M, Gu L, Cui F, Lu QB. Detecting and genotyping high-risk human papillomavirus among male patients during 2015-2023 in Beijing, China. Emerging microbes & infections, 2024, 13, 1, p.2313848
- Fiegl A, Hartmann A, Junker K, Mink J, Stoehr R. [Pathology and molecular pathology of carcinoma of the penis]. Pathologie (Heidelberg, Germany), 2025, 46, 1, p.34-39
ページ監修:総院長「葉山芳貴」紹介

総院長、医学博士 葉山芳貴
経歴
- 平成14年
- 聖マリアンナ医科大学 卒業
- 平成20年
- 大阪医科大学 大学院 卒業
- 平成22年
- 大手美容形成外科 院長 就任
- 平成27年
- メンズサポートクリニック開設
- 平成28年
- メンズサポートクリニック新宿 院長就任
- 平成28年
- 医療法人清佑会 理事長 就任
資格
医師免許(医籍登録番号:453182)
保険医登録(保険医登録番号:阪医52752)